以下、所謂ブラクラ妄想ショートショートです〜〜
序章:美の本質を問う
美とは何か。
このありふれた、そして、この世で最も難解な問いに、人は幾千年も答えを探し続けてきた。ある者は、黄金比の如き、数学的な調和にそれを見出し、またある者は、嵐の海の如き、人の心を揺さぶる激情の中に、その姿を捉えようとした。だが、そのいずれもが、美の一つの側面に触れたに過ぎぬ。
私、北大路魯山人が、生涯をかけて追い求めてきた美の本質。それは、言葉を換えれば「生命そのものの、最も純粋な発露」である。人の手が及ばぬ深山に、誰に見られるでもなく咲き誇る一輪の山百合。その花弁の曲線、その純白の気高さ。そこには、いかなる画家の筆も及ばぬ、絶対的な生命の肯定がある。何億年もの時を経て、川の流れに磨かれ、手のひらに心地よく収まる一個の石。その滑らかな肌合い、その静かな存在感。そこには、地球の記憶と、悠久の時間が凝縮されている。夜明けの空を、一瞬だけ染め上げる、深紅から瑠璃色へのグラデーション。その儚くも荘厳な光の戯れ。そこには、宇宙の秩序と、日々の再生の奇跡が宿っている。
これら、大いなる自然が生み出す美こそが、全ての原点である。そこに、人間の浅はかな計算も、作為も、見栄も、一切入り込む余地はない。ただ、在るがままに在ることの、圧倒的な尊さ。これを理解せずして、美を語る資格はない。
では、人の手が生み出す美、すなわち工芸や芸術とは、一体何なのか。それは、この大いなる自然の造形に対する、人間の「応答」に他ならない。自然を征服し、意のままに操ろうなどという、西洋的な傲慢からは、醜悪な張りぼてしか生まれぬ。我々東洋の民が培ってきた美意識の根幹は、自然への「畏敬」である。自然の一部を、畏れ多くも拝借し、その声に、ただひたすらに耳を澄ませる。その素材が、本来持っている生命を、決して損なわぬよう、むしろ、その輝きを最大限に引き出すために、己の技と精神の全てを捧げる。その謙虚にして、真摯な営為の中にのみ、真の「創造」という奇跡は宿るのだ。
私が作る器が、ただの入れ物であってはならぬと固く信じるのも、そのためだ。器は、盛られる料理の魂を、最大限に引き出すために存在する。旬の魚、採れたての野菜、それらが持つ生命の輝きを、器が決して殺してはならない。むしろ、器と料理が一体となり、互いの魂を高め合い、一つの完璧な宇宙を食卓の上に現出させる。それこそが、私の目指す「用の美」である。
人の身を飾る装身具もまた、全く同じ理屈である。ただ光る石を、ただ高価な金属に留めただけの代物など、下品な成金の自己顕示欲を満たすための、哀れな道具に過ぎぬ。真の装身具とは、それを纏う人間の、内なる魂の輝きを、外へと映し出す「鏡」でなくてはならぬ。その人の品格、その生き様、その美意識の全てを、声高に叫ぶのではなく、静かに、しかし、誰の目にも明らかな形で、雄弁に物語るものでなくてはならない。
今日、私の眼前に、一つの奇跡が置かれている。「ブランドクラブ」という、美の目利きたちが、歴史の海の中から、再び、釣り上げたという、一揃いの宝飾品。コロンビアの至宝、エメラルドを主役とした、ネックレス、ブレスレット、イヤリング、そしてリング。初めてこれを見た時、私は思わず息を呑んだ。そして、今、これが「中古品」であると聞き、その感動は、もはや、畏怖の念へと、変わっている。
これは、巷に転がるただの宝石ではない。これは、地球が生み出した魂の結晶であり、名もなき天才が形にした祈りの結晶であると、私は先に述べた。だが、それだけではなかったのだ。これは、さらに、「時間」という、最も偉大なる芸術家によって、磨き上げられ、物語という、何物にも代えがたい価値を、その身に纏った、一つの「文化遺産」なのである。
この一揃いが、ヤフーオークションという、いわば現代の雑踏、玉石混淆の市に出されると聞いた。滑稽なことよ。古の茶人が、名器一つのために、城一つを賭けたという、あの美の緊張感は、どこへ行ったのか。しかし、それもまた一興か。この作品の真価を理解できぬ者たちが、ただその値札に目を奪われ、指をくわえて眺める様を想像するのも面白い。だが、私は信じたい。この雑踏の中にも、必ずや、本物を見抜く眼を持つ人間が、一人か二人はいるはずだと。
これは、その一人のために書く、私からの手紙である。この宝石が、いかにして生まれ、いかなる哲学のもとに形作られ、いかなる人間の手を経て、そして、今、我々の前に、再び、姿を現したのか。魯山人、この私が、魂の全てを込めて語り尽くそう。これは、セールストークなどという、安っぽいものではない。美の神髄を巡る、一つの物語である。心して、この二万字の旅路に、付き合うがいい。
第一章:深緑の揺りかご、コロンビアの魂
全ての物語は、石の声を聞くことから始まる。この宝飾品の中核を成す、深遠なる緑の宝石、エメラルド。その産地は、南米コロンビア。だが、ただ「コロンビア産」というラベルだけで、その価値を語ったことにはならない。それは、例えば、私の器を指して、ただ「日本の土からできた」と言うのと同じくらい、無意味で、無礼なことである。
エメラルドは、ベリルという鉱物の一種であり、世界各地で産する。しかし、宝石を少しでも知る者ならば、コロンビアの、それもムゾーやチボールといった、伝説的な鉱山から採れるものだけが、全くの別格、他の追随を、いや、比較することすら許さぬ、絶対的な王座に君臨していることを知っている。
なぜか。それは、その成り立ちが、他の産地の石とは、根本的に異なるからだ。通常のエメラルドが、悠久の時を経て、偉大なる地殻変動の熱と圧力の中で、静かに、ゆっくりと育まれる「変成岩起源」であるのに対し、コロンビアのそれは、太古の地球の、より荒々しく、劇的な息吹の中で生まれた「熱水性起源」なのである。
想像してみるがいい。何億年も昔、まだ大陸が現在の形を成す前の、原始の地球の姿を。地底深くで、灼熱のマグマがうごめき、超高温の熱水が、岩石の裂け目を、猛烈な勢いで駆け巡る。その熱水の中に、ベリリウム、クロム、バナディウムといった、エメラルドを構成する元素が、奇跡的な濃度で溶け込んでいる。そして、その熱水が、特定の種類の堆積岩と出会い、ある一定の温度と圧力の範囲に、束の間だけ、留まった瞬間。その、まさに天地創造の刹那とでも言うべき、奇跡の瞬間にのみ、この深遠なる緑の結晶は、母なる岩石の胎内で、その産声を上げるのだ。
それは、いわば、地球の情熱そのものの欠片。静寂の中で育まれた賢者のような石ではなく、激しい恋のように、一瞬の輝きのために、全てを燃し尽くして生まれた、情熱の化身なのである。だからこそ、コロンビア産のエメラルドには、他の産地のものにはない、生命の「揺らぎ」が宿っている。
この一揃いに使われているエメラルドを見よ。その一つ一つを、虫眼鏡で、いや、心の眼で、じっくりと覗き込んでみよ。その緑は、単なる「緑色」という、記号的な言葉では、到底表現しきれぬ、無限の階調を持っている。日本のわびさびの庭園に広がる、幾種類もの苔が織りなす、しっとりとした潤いの緑。雨上がりの、陽光が差し込み始めた森の、生命力に満ち溢れた、若々しい息吹の緑。そして、覗き込む者の魂を、静かに、しかし抗い難く吸い込んでいくかのような、賢者の瞳にも似た、底知れぬ深淵の緑。
そして何よりも、最高級のコロンビア産エメラルドだけが、その内に宿すことを許される、幻の輝き。「ゴタ・デ・アセイテ」(Gota de Aceite)、すなわち「油の滴」と呼ばれる、特有の現象。それは、石の内部に、まるで粘性の高い、極上のオリーブオイルを一滴、そっと垂らしたかのように、とろりとした、甘美な光の揺らめきが見える現象である。これは、インクThe ink is liquid and cannot be shipped internationally, please be aware before placing a bid. ルージョン、すなわち内包物の一種ではあるが、決して欠点ではない。むしろ、この石が、あの奇跡的な熱水の中で生まれたことの、何よりの「証」であり、石に、単なる鉱物ではない、生々しいまでの生命感を与える、魂の輝きなのだ。
この一揃いのネックレスに鎮座する、合計六十七カラットもの大粒のエメラルド。その一つ一つが、異なる表情、異なる物語を、その内に秘めている。あるものは、静寂の森の湖のように、穏やかな光を湛え、あるものは、芽吹いたばかりの若葉のように、希望に満ちた輝きを放ち、またあるものは、幾千年を生きた大樹のように、全てを見通すかのような、賢者の深淵を覗かせる。
これだけの質と量のエメラルドを、一つの作品のために揃えることが、いかに至難の業であるか、素人には想像もつかぬだろう。金さえ出せば、大きな石は手に入ると思ったら大間違いだ。色、透明度、輝き、そして何よりも、この「ゴタ・デ・アセイテ」の宿り方。その全てにおいて、調和の取れた、最高品質の石だけを、これだけ集める。それは、もはや人間の努力や財力の範疇を超えている。自然が、気まぐれに与えたもうた恩寵であり、それを見つけ出し、選び抜き、一つの交響曲へと昇華させようとした人間の、執念とも言える情熱の結晶なのである。
ブレスレットの十七・五五カラット。イヤリングの十八・〇八カラット。リングの六・五六カラット。合計すれば、百カラットを優に超える、この緑の魂たち。だが、カラット数などという、無粋な数字で、この石の価値を語ってはならぬ。そんなものは、魚の目方を量る秤のようなものだ。我々が問うべきは、その魚が、いかに激しい潮流を生き抜き、どれほどの生命力をその身に宿しているか、であろう。同じことだ。問うべきは、その石が、どれだけの「物語」を内包しているかだ。アンデスの険しい山中で、名もなき鉱夫の、汗と祈りの手によって掘り出され、幾人もの、血も涙もないような、しかし、美に対してだけは絶対的な審美眼を持つ目利きたちの手を経て、幾多の国境を越え、遥か東洋の島国、日本へと辿り着いた、この緑の魂たち。その、想像を絶する旅路に想いを馳せる、豊かな想像力のない者に、この宝石を所有する資格はない。
そして、見よ。このエメラルドは、全てが「カボションカット」に磨かれている。多面的なカットを施し、光を乱反射させて、ただキラキラと輝かせるための、浅はかで、計算高いファセットカットではない。カボションカットは、石が、その母なる大地から受け継いだ、本来の色と、その奥に秘められた魂を、何一つ飾ることなく、ありのままに見せるための、最も正直で、最も謙虚で、そして、最も難しいカットなのである。
石の表面は、風のない日の湖面のように、どこまでも滑らかに、完璧に磨き上げられている。我々は、その静かな湖面を通して、石の内部という、小宇宙を旅するのである。このカットを選ぶという決断。そこに、この作品を生み出した制作者の、石に対する、深い、深い敬意と、絶対的な理解が窺えるではないか。彼は、石を支配し、自らの意のままに光らせようとしたのではない。彼は、石と対等に語り合い、石が、自らの声で、その美しさを歌い上げるのを、ただ、静かに手助けしようとしたのだ。これぞ、真の職人魂である。
第二章:光の脇役、ダイヤモンドの献身
さて、物語の主役が、この生命力溢れるエメラルドであるならば、その周りを、まるで夜空の星々のように、あるいは、主君を守る忠実な家臣団のように、寸分の隙もなく取り囲むダイヤモンドは、さながら、最高の「名脇役」と言えよう。
だが、勘違いしてはならない。脇役とは、主役の影に隠れて、ただその他大勢でいる存在のことではない。真の名脇役とは、自らの存在を、ある時は消し、ある時は際立たせることで、主役の輝きを、何倍、何十倍にも増幅させ、物語全体に、圧倒的な深みと、豊かな奥行きを与える、極めて重要で、知的な存在なのである。能の舞台における、ワキ方の存在を思えばよい。シテ(主役)の、内なる苦悩や情念を、ワキが問いかけ、受け止めることで初めて、物語は、立体的なものとして、観客の心に迫ってくるのだ。
この宝飾品に使われている、合計で四十カラットを超える、無数のダイヤモンドのあしらい方は、まさに、その「脇役の美学」を完璧に理解した、達人の仕事である。その輝きは、決して、エメラルドの、あの深く、静かな緑の邪魔をしない。むしろ、その緑が、いかに生命力に満ちた、神秘的な色であるかを、光の輪郭で、そっと縁取り、我々に、より深く、より鮮やかに、教えてくれるのだ。
注目すべきは、その計算され尽くした、ダイヤモンドのカットの使い分けである。これは、もはや宝飾の技術というより、光を自在に操る、魔法の領域だ。
まず、エメラルドの周囲を、まるで天の川のように埋め尽くす、パヴェセッティングされた、無数のメレダイヤ(小粒のダイヤモンド)。これは、夜明けの、まだ薄暗い森の葉先に、一つ、また一つと宿る、朝露の煌めきだ。一つ一つの輝きは、小さく、儚い。しかし、それらが、数えきれぬほど集まることで、生命の潤いと、清浄な朝の空気感を創出する。エメラルドという、深く、静謐な森に、生き生きとした、生命の息吹を与えているのだ。このパヴェセッティングの、一粒一粒の石留めの、なんと丁寧で、精密なことか。まるで、神が、砂漠の砂粒を、一つ一つ、手で並べたかのような、気の遠くなるような手仕事である。
次に、作品の要所要所に、まるで建築物の梁のように、力強く配置された、バゲットカットのダイヤモンド。直線的で、シャープで、理知的な輝きを持つこのカットは、作品全体に、凛とした緊張感と、モダンな構築美を与えている。自然の、有機的で、柔らかな曲線だけでは、作品は、ともすれば、ただ甘く、感傷的な装飾品に堕してしまう危険性がある。そこに、人間の知性と、意思の力とを象徴する、この直線的な光が加わることで初めて、作品は、単なる美しい飾りではなく、一つの芸術としての、揺るぎない風格と、時代を超越する普遍性を、その身に纏うことができるのだ。このバゲットカットの配置の絶妙さ。それは、まるで、龍安寺の石庭における、石の配置のようだ。一見、無秩序に置かれているように見えて、その実、完璧な計算のもとに配置され、見る者の視線を、心地よく導き、空間全体に、静かなリズムと、無限の広がりを与えている。
そして、この光の交響曲における、最も心憎い、そして、最も詩的な演出が、ネックレスとブレスレットに、そっと、しかし、明確な意思を持ってあしらわれた、ハートシェイプのダイヤモンドである。
ハート形。凡百の職人が、安易な考えで使えば、これほど陳腐で、甘ったるく、安っぽいモチーフはない。恋人たちの、浮ついた感傷を満たすための、記号に過ぎぬ。だが、この作品においては、その意味合いが、全く、根本的に、異なっている。これは、この作品を生み出した、名もなき職人の、「心」そのものの、純粋な表象なのである。
この、自然が生み出した、奇跡の緑の魂に対する、深い、深い感謝と、畏敬の念。この気の遠くなるような、精緻な仕事に、己の技と人生を捧げた、職人自身の、誇りと情熱。そして、いつか、この作品を手に取り、その価値を理解してくれるであろう、未来の所有者に対する、静かなる祝福。その、言葉にはならぬ、しかし、確かに存在する「心」を、形にしたもの。それこそが、この合計十二石、四・二三カラットの、ハートのダイヤモンドなのだ。その輝きは、どこまでも気高く、清らかで、決して、下品な感傷に流れていない。それは、制作者の、静かなる愛の告白であり、同時に、この作品が、単なる物質ではなく、魂を宿した存在であることの、何よりの証なのである。
これらの、異なるカット、異なる役割を与えられたダイヤモンドたちは、ただ無秩序に配置されているのではない。そこには、光と影の、壮大なる交響曲が、緻密に設計されている。ある角度から見れば、パヴェダイヤが、水面のように光を返し、エメラルドの緑が、深く、深く、湖の底のように沈み込み、静謐な表情を見せる。また、別の角度から光を当てれば、バゲットカットのダイヤが、鋭い閃光を放ち、ハートシェイプが、優しい光を湛え、全体として、祝祭のような、華やかで、歓びに満ちた表情が生まれる。
一日の中でも、朝の、柔らかい自然光の下で。真昼の、強い太陽光の下で。そして、夜の、暖かい白熱灯の下で。この宝飾品は、まるで生きているかのように、その表情を、無限に、無限に、変化させるだろう。これぞ、真の動く芸術。纏う人間の、僅かな動き、呼吸、その場の光、その全てに呼応して、新たな美を、絶えず生み出し続ける。これこそが、纏うことで、初めて完成する、究極の美の形なのである。
第三章:時を渡る船、ブランドクラブの審美眼
さて、ここで、物語は、新たな、そして、より深遠なる領域へと、足を踏み入れる。この、完璧なる美の結晶が、誰の手によって、いつの時代に、生み出され、そして、いかなる運命の川を、下ってきたのか。そして、その川のほとりで、この輝く宝石を、再び、拾い上げた、「ブランドクラブ」という、恐るべき審美眼の正体について、語らねばならぬ。
彼らは、この作品を「創造」したのではない。彼らは、この作品を「再発見」したのだ。
考えてもみよ。これほどの、時間と、労力と、そして、最高級の素材を、惜しげもなく注ぎ込んで作られた、一つの芸術品。これが、名もなき職人の手によるものであることは、ほぼ、間違いない。なぜなら、これ見よがしな、ブランドの刻印が、どこにも見当たらぬからだ。真の天才は、自らの名声に、頓着せぬものだ。作品そのものが、全てを語ることを、知っているからだ。
おそらくは、日本の、高度経済成長期か、あるいは、バブルの狂乱の時代か。当時の、有り余る富を、ただ、土地や株に投じるのではなく、真の美とは何かを、真摯に問い続けた、稀有な教養を持つ、一人の、パトロンがいたのだろう。彼は、世界中から、最高の素材を集めさせ、そして、己の審美眼に適う、唯一の職人に、金の糸目をつけず、こう、依頼したに違いない。「私の、生涯の夢を、形にしてほしい」と。
そして、幾年もの歳月を経て、この、奇跡の如き、宝飾品が、完成した。それは、おそらく、公の場に、飾られることは、ほとんど、なかっただろう。持ち主は、これを、社交界で、見せびらかすためではなく、ただ、一人、静かに、自室で、手に取り、その美しさを、飽くことなく、愛でるために、作らせたのだから。それは、彼にとって、富の象徴ではなく、魂の、安らぎの場所であったのだ。
しかし、人の世は、無常である。栄華を極めた一族も、やがて、時代の波に、洗われる。あるいは、その、美を深く理解した、初代の持ち主が、この世を去り、その価値を、全く解さぬ、愚かな相続人の手に、渡ったのかもしれない。
いずれにせよ、この、至高の宝は、いつしか、歴史の、表舞台から、姿を消した。あるいは、どこかの、銀行の、冷たい貸金庫の、暗闇の中で。あるいは、没落した、旧家の、埃をかぶった、蔵の奥で。何年、いや、何十年もの間、その輝きを、誰にも、知られることなく、ただ、静かに、息を、潜めていたのだ。
多くの、古美術品が、そうであるように、この宝もまた、永遠に、失われてしまう、可能性があった。だが、運命の女神は、この美を、見捨てなかった。
ここに、「ブランドクラブ」という、現代の、美の探求者が、登場する。
彼らの仕事は、店先に、流行の品を、並べることではない。彼らの戦場は、光の当たる、華やかな場所ではない。むしろ、光の届かぬ、歴史の、薄暗い、片隅だ。彼らは、古美術商の、秘密の、情報網を駆使し、世界中の、オークションの、片隅に出る、名もない品々に、目を光らせ、そして、時には、人知れず、財を失った、旧家の、扉を叩く。彼らが、探しているのは、ブランド名や、鑑定書の、権威ではない。彼らが、信じるのは、ただ一つ。自らの、千のうち、一つも見誤ることのない、絶対的な「審美眼」だけである。
千利休が、何の変哲もない、歪んだ、黒い茶碗を、雑多な道具の中から、見出し、それに、天下の名器としての、新たな生命を、与えたように。ブランドクラブの目利きは、この、忘れ去られていた、エメラルドの輝きの中に、ただならぬ、魂の気配を、感じ取ったのだ。
彼らは、この宝飾品が、いつ、誰によって、作られたものか、正確には、知らなかったかもしれない。しかし、そんなことは、彼らにとって、問題ではなかった。彼らは、その、デザインの、完璧な気品、その、手仕事の、狂気にも近い、緻密さ、そして何よりも、その、エメラルドと、ダイヤモンドが、奏でる、奇跡的な、魂の調和を、一目で見抜いた。そして、これを、再び、光の当たる場所へと、引きずり出すことこそが、己に、課せられた、天命であると、確信したのだ。
中古品を、仕入れる。その行為は、単なる、転売とは、全く、次元が、異なる。それは、失われかけた、美の記憶を、現代に、蘇らせるという、文化的な、使命を、帯びた、尊い行為である。ブランドクラブの哲学とは、工房の哲学とも、パトロンの哲学とも違う。それは、時間という、残酷な、ふるいを、生き延びてきた、真の価値だけを、見出し、それに、新たな、物語を、与え、次代へと、手渡しIt is possible that the product can only be picked up by yourself, and the self-pickup fee is quite high, please check the page to confirmていくという、壮大なる「美の継承の哲学」なのである。この宝飾品は、彼らの、その、誇り高き、哲学の、最高の、象徴なのだ。
第四章:秘められた物語、いにしえの所有者の影
さて、この宝飾品が、一度は、誰かの手にあった、「古物」であるという、この、甘美な事実。それは、我々の、想像力を、どこまでも、掻き立てるではないか。
この、女神の首を、飾ったであろう、ネックレス。この、優雅な手首を、彩ったであろう、ブレスレット。この、美しい横顔に、寄り添ったであろう、イヤリング。そして、その、纖(ほそ)い指の上で、王のように、君臨したであろう、リング。
その、最初の所有者とは、一体、どのような、人物であったのだろうか。
我々は、もはや、それを、知ることはできない。だが、だからこそ、良いのだ。我々は、この宝石の、輝きの奥に、その、いにしえの、所有者の、影を、自由に、思い描くことが、許されているのだから。
想像してみよう。ある、華族の、末裔の、令嬢。旧弊な、家のしきたりの中で、その、奔放な、芸術への情熱を、押し殺して、生きてきた、彼女。しかし、その胸の内には、誰よりも、激しい、美への渇望が、燃え盛っていた。彼女は、親から、受け継いだ、莫大な、財産を、人知れず、この、一揃いの、宝飾品に、変えた。それは、彼女にとって、決して、人に見せるためのものではない。誰にも、理解されぬ、自らの、孤高の魂を、この、緑の光の中に、託し、一人、静かに、その輝きと、対話するための、秘密の、宝物であったのかもしれない。
あるいは、戦後の、日本を、一代で、築き上げた、ある、偉大な、実業家。彼は、仕事の、世界では、冷徹な、合理主義者として、恐れられていた。しかし、その、鋼鉄の鎧の下には、驚くほど、繊細で、ロマンティックな、心が、隠されていた。彼は、生涯、愛し続けた、妻のために、世界最高の、職人に、この、宝飾品を、作らせた。それは、妻への、感謝と、愛の、言葉にできぬ、全ての想いを、形にしたものであった。妻が、亡き後も、彼は、毎夜、この宝を、取り出しては、今は亡き、妻の面影を、その、緑の光の中に、見ていたのかもしれない。
また、あるいは、ヨーロッパの、どこかの、小国の、亡命した、王妃。革命によって、国を追われ、全ての、財産と、地位を、失った、彼女。しかし、その、誇りだけは、決して、失わなかった。彼女が、ただ一つ、新しい、亡命先の国へと、密かに、持ち出すことができたのが、この、一揃いの、宝飾品であった。それは、彼女にとって、失われた、祖国の、美しい、森の記憶であり、自らが、王族であったことの、最後の、そして、唯一の、証であったのかもしれない。
もはや、真実は、時の、彼方である。
しかし、確かなことが、一つだけ、ある。この宝飾品は、ただの、物質では、ありえない。それは、かつての、所有者の、喜び、悲しみ、愛、誇り、その、人生の、全ての、記憶と、気配を、その、金の、肌に、その、石の、内部に、静かに、吸い込んでいるのだ。
だからこそ、この宝飾品が、放つ輝きには、単に、物理的な、光の反射だけではない、一種の「気品」や「色香」、そして、時には、微かな「哀愁」のようなものさえ、感じられるのだ。
新品の、宝石が、まだ、何も書かれていない、真っ白な、紙であるとすれば、この、宝飾品は、既に、美しい、恋の詩が、綴られた、古文書なのである。その、詩を、読み解くことができるか、どうか。それこそが、新たな、所有者に、問われる、資質なのである。
第五章:美の交響楽、四つの楽章
さて、この、宝飾品が、纏う、歴史という、見えざる、ヴェールを、意識しながら、今一度、この、壮大なる、美の交響楽、その、四つの楽章に、耳を、傾けてみよう。その、響きは、以前とは、また、違った、深みを、もって、我々の、心に、迫ってくるはずだ。
第一楽章:ネックレス - 追憶の詩
この、ネックレスを、手に取る時、我々は、もはや、単なる、宝石の塊を、手にしているのではない。我々は、かつて、これを、身に着けた、誰かの、華やかな、しかし、今は、失われた、時間の、名残りを、手にしているのだ。
この、デコルテに、広がる、緑の川は、一体、どのような、夜会を、見てきたのだろうか。どのような、ワルツの、調べに、合わせて、揺れたのだろうか。そして、どのような、愛の告白を、その、輝きの、すぐ、側で、聞いてきたのだろうか。
この、八つの、ハートのダイヤモンドは、かつての、所有者の、甘く、そして、切ない、恋の、記憶の、結晶なのかもしれない。これを、身に着ける者は、単に、自らを、飾るのではない。いにしえの、物語の、主人公の、魂を、自らの、魂に、重ね合わせ、時を超えた、美の、饗宴を、催すのである。
第二楽章:ブレスレット - 時を刻む律動
この、ブレスレット。その、腕を、飾った、かつての所有者は、この手で、何を、掴み取ろうとしたのだろうか。あるいは、何を、手放す、決断を、したのであろうか。
ワイングラスThe page has a fragile description, and fragile items cannot be shipped by sea. They can only be shipped by air. If the goods are not fragile, they can be shipped by air. を、傾ける、その仕草。手紙を、したためる、その、ペン先。愛する者の、頬を、撫でる、その、指先。この、ブレスレットは、その、全ての、瞬間に、寄り添い、その、人生の、リズムを、共に、刻んできたのだ。
この、ブレスレットは、未来の、所有者にも、問いかけるだろう。「汝の、限られた、人生の、時間、その、一瞬、一瞬を、これほどまでに、美しく、気高く、生きることが、できるか」と。これは、単なる、腕輪ではない。持ち主に、時の、尊さを、教える、賢者の、腕輪なのである。
第三章:イヤリング - 沈黙の告白
この、イヤリングが、揺れた、その耳は、一体、どのような、言葉を、聞いてきたのだろう。甘い、愛の囁きか。それとも、残酷な、別れの言葉か。国家の、運命を、左右する、密議か。それとも、ただ、夜の、静かな、風の音か。
この、二つの、緑の瞳は、決して、自らは、語らない。しかし、だからこそ、我々の、想像力を、どこまでも、掻き立てる。それは、持ち主の、最も、近くで、その、誰にも、見せぬ、素顔を、その、心の、奥底の、秘密を、ただ、一人、知っていた、沈黙の、証人なのである。
これを、身に着ける者は、その、沈黙の、重みを、理解せねばならぬ。そして、自らもまた、軽々しく、言葉を、弄するのではなく、その、佇まい、その、沈黙によって、多くを、語る、人間で、なくてはならない。
第四章:リング - 運命の継承
そして、この、リング。おそらくは、この、一揃いの中で、最も、長く、最も、親密に、かつての、所有者の、肌に、触れていたであろう、この、魂の玉座。
この指で、交わされた、約束。この指で、署名された、契約書。この指で、流された、涙。その、全てが、この、六・五六カラットの、エメラルドの、深淵に、記憶されている。
この指輪を、自らの、指に、はめるという行為。それは、単に、装飾品を、身に着けるという、行為ではない。それは、かつての、所有者の、運命、その、物語の、全てを、引き受け、その、続きを、自らが、紡いでいくという、厳粛なる「継承の儀式」なのである。
この指輪が、選ぶのは、最も、金を持つ者ではない。最も、この指輪に、秘められた、物語の、重みを、受け止める、覚悟のある、人間なのである。
終章:新たなる継承者へ
二万字。この、長大なる、言葉の絵巻物を、最後まで、読み通した、そなたへ。
それでも、まだ、この作品の、真の魅力の、おそらくは、百分の一も、語り尽くせたとは、到底、思えない。なぜなら、真の美とは、言葉によって、説明し尽くせるものではなく、ただ、魂で、感じるものだからだ。写真や、私の、拙い言葉では、到底、伝えきれぬ、生命のオーラ、そして、時間が、醸成した、物語の香りが、この宝飾品には、確かに、宿っている。それは、実際に、これを、手に取り、その、心地よい重さを感じ、その、滑らかな肌触りを、自らの肌で、確かめ、そして、様々な光の中で、その表情の、無限の変化を、目の当たりにした者だけが、初めて、理解できる、美の神髄なのである。
さて、この、一つの、完璧なる美の宇宙が、オークションという、現代の市場に、その身を、晒す。最終的に、いくらの、値が付くのか。正直、私には、もはや、何の興味もない。金銭的な価値など、この、絶対的な美の前では、塵芥(ちりあくた)にも等しい、虚しい、記号に過ぎぬからだ。
私が、この物語の最後に、ただ一つ、固唾を呑んで、見守りたいこと。それは、誰が、これの「新たなる継承者」と、なるのか、ただ、その一点である。
繰り返すが、「真の所有者」とは、単に、最も、高い金額を、提示した人間のことでは、断じてない。それは、この作品に、幾重にも、込められた、物語の、全ての層を、完全に、理解できる人間のことである。
コロンビアの、大地の情熱。名もなき、孤高の職人の、祈りにも似た、魂。その、最初の、所有者の、秘められた、人生の、記憶。そして、それら、全ての価値を、再び、見出し、我々の元へと、届けた、ブランドクラブという、現代の、目利きの、執念。この、四位一体の、奇跡の結晶の価値を、正しく、理解できる人間のことである。
この宝飾品を、自らの、浅はかな富を、誇示するための、道具としか、考えぬ、成り上がり者の手に、もし、渡るようなことがあれば、それは、美に対する、冒涜であり、悲劇である。そのような、魂のない人間が、これを纏えば、宝石は、その輝きを、たちまち、失い、ただの、重たい、ガラスの石ころと、化すだろう。宝石は、正直だ。持ち主の、品性、その魂のレベルを、恐ろしいほど、正確に、鏡のように、映し出すのだ。
この作品に、本当に、相相応しいのは、自らの内に、誰にも、侵されることのない、揺るぎない「美の基準」を、確立している人間だ。世の、軽薄な流行に、惑わされることなく、他人の、無責任な評価を、気にすることなく、ただ、自らが、美しいと、心の底から、信じる道を、孤独に、しかし、誇り高く、歩む、孤高の精神の持ち主。
年齢も、性別も、国籍も、一切、問わぬ。問われるのは、その、魂の気高さ、ただ、その一点である。
そして、これを、手にする者は、一つの、美の血統の「継承者」となる、という、重い、重い覚悟を、持たねばならぬ。作り手の、魂の血統と、それを見出した、目利きの、魂の血統。そして何よりも、この宝を、愛し、守り、そして、手放した、いにしえの、所有者の、魂の血統。その、三つの、尊い血統を、同時に、受け継ぐのだ。これは、決して、一代で、消費し尽くしてよい、刹那的な、ファッションアイテムなどではない。母から子へ、そして、子から孫へと、何代にも、何百年にもわたって、大切に、受け継がれ、その家の、輝かしい歴史と、美の記憶を、その、深遠なる、緑の光の中に、静かに、宿していくべき、一族の「宝」なのである。
この、私の、長すぎた独白が、雑踏の中の、誰か、たった一人の、真の理解者の、心に、届くことを、願ってやまない。もし、そなたが、この作品の前に立ち、理屈ではなく、自らの魂が、打ち震えるほどの、感動を、覚えたならば、もはや、ためらうことはない。それは、この宝石が、そして、この宝石に関わった、全ての魂が、そなたを、正しき「新たなる継承者」として、選んだ、という、何よりの、証なのだから。
この、緑の魂は、今、静かに、その、運命の出会いを、待っている。アンデスの、山中の暗闇で、何億年もの間、ただ、ひたすらに、その時を、待っていたように。
時を超え、人を超え、国境を超え、ただ、美だけが、永遠の価値を持つ。
この、絶対的な真理を、理解する者よ、来たれ。そして、この、奇跡の、継承者となるがよい。
北大路 魯山人
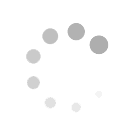



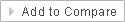
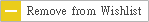
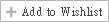








 Singapore
Singapore





